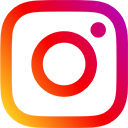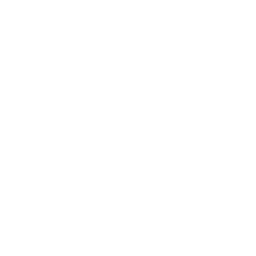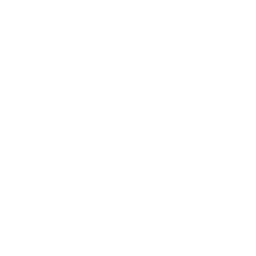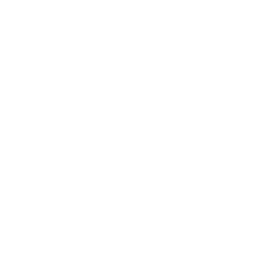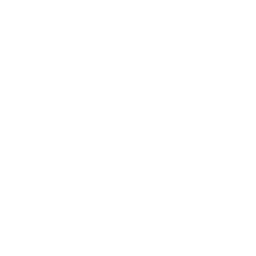使いやすい器とは
使いやすい器とはどんなものでしょうか?
軽いこと、持ちやすいこと、シチュエーションに合うこと、手入れがめんどくさくない、、
などなど色々あるかと思います。
使い手にとって、作り手にとって「使いやすい器」への考え方は異なりますが、現在の私が考える使いやすいはこうです。
それは、”丁度よい重さ”であること。
…これまた人によるところが大きい答えですが、私を教えて下さった先生は「いい器というのは、重心の在りかが分からない器だ」と仰られていました。どういうことかと言うと、器を持った時にたとえ肉厚な器だったとしても不思議と重さを感じにくかったり、飲み物を入れる前の器と入れたあとの器を持ち比べた時に、飲み物を入れた状態の器のほうがなんだかしっくりきたり、、、
要するに、器を手に取った時の違和感やストレスを取り除いた器が、いい器だと言えるのではないか?と私は考えています。
うつわの重さ
実際にうつわを購入を考えるお客様からしたら、好みの器、使いたい器とはどんなものでしょう。
これまで私がお会いしたお客様の声を思い出すと、最近は「軽いうつわ」が最も多い感想でした。理由の多くは、手に持つときにずっしりくると重くて疲れてしまう。そこに料理を入れるとなると余計に重くなり、形や色が気に入っていてもいつの間にか食器棚の肥やしになってしまっている。。
ご年配のお客様からは特に「重さ」に対する意見が多かったです。洗い物も疲れてしまいますしね。。笑
もちろん、軽いだけが器の良しあしを決めるわけではありません。例えばうつわの色によってもイメージが変わります。黒い器で重厚感を出すなら少し重ための方が雰囲気がある、、
そう、結構雰囲気って大事だと思います。「なんかいい」「コンセプトに合ってる」そういった感覚を持ってもらえるなら、それはいい器と言えるかもしれません。私の器なら、ベースはアイボリー調で優しい見た目をしていますが、一見重そうに感じるみたいです。ただ薄く、軽めに作っているため手に持って頂いたときにギャップを感じ感動してもらえることが多いです。なんだかそういうふうに思ってもらえるのって嬉しいんですよね。
持ちやすさ
軽くてデザインもよくて気に入った器が見つかった!!と思っても次の瞬間、、「ん?持ちにくい、、、」
こうして購入を辞めてしまうお客様を見る機会も過去にありました。
例えばご飯茶碗は、毎日使う器の一つですよね。大体の人はお茶碗の口元と底のあたりに指をひっかけてお持ちになるかと思います。器の底の机と面している部分のことを「高台」(こうだい)と言うのですが、そこに指をひっかけた時の引っ掛かり具合が器を持ったときの心地よさに大きく影響しています。
高台の深さが浅いと指が引っ掛かりにくくて落としてしまいそう、、、と不安を感じたり、高台の角度が鋭角だったり鈍角だったりしてもその持ちやすさは変わります。正直好みが分かれる部分ではあるのですが、、笑。
好みはあるにせよ、自然に違和感なく持てる、不安を感じない器に仕上げたいものです。
バランス
まぁ、、結局大事なのってバランスですよね(笑)。いつもお客様が作品を吟味されているところを見るに、色んな持ち方をしてみたり、様々な角度から見たり、器を持ったまま上下に軽く振って重心や重さを確認してみたり、、
これらの行動って、色んな視点で器のバランスの良さを見たいからしている行動なのだと思います。私自身、他の作家さんから器を見るときにしていることでもあります。ただプロ目線と言いますか、作っている人独特の動きや見方をするのですぐ「同業者の方ですか?」とばれてしまいますが(笑)。
器の厚みを指で挟みつつ上下にスライドさせて図ったり、器を軽く指で弾いて音を感じて陶器か磁器か判断したり、マグカップの取手のつけ具合や釉薬、色の出方を見たり・・・この辺はかなりマニアックになるため、他の記事のテーマにしてみたいと思います笑。
例外として、家庭用の器と飲食店用の器では使い勝手も使用目的も異なります。サーブしやすいようにしたり、敢えて使いにくくしてデザイン性を高めたり、コース料理の器等だと家庭用より料理をちょこんと載せるくらいの容量にしてみたりと色々ありますね。
他にも各々のお家のカラーにあった器や食卓の雰囲気、大皿やワンプレートで食事を出すのか小鉢など器を沢山出す食卓なのかなどでも、買い手の「使いやすい器」への考え方は変わるでしょう。
ただ今回のまとめとしては、大抵どんな人でも気にする「使いやすい」に着目した点として、”丁度良い重さであること”、”持ちやすいこと”、”バランスがいいこと”が使いやすい器と感じて頂ける条件かなと考える次第です。
読者の皆様も、どうして私はこの器を選んだのだろう?どうして使いやすそうと感じたのだろう?とふと器選びの時に考えてみると、自分の求める器にもっと出会いやすくなるかもしれませんね。ぜひ作家さんがいるところでしたら、話しかけてみて楽しんで器選びしてくださいね!